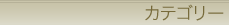ブログ個人トップ | 経営者会報 (社長ブログ)
「店がブランドになる」ことを支援・プロデュース! コンサルティング会社・社長のジャム・セッション
- ブログトップ
- ブログ個人トップ
前ページ
次ページ
「小さくても光り輝くブランド」をプロデュースしているクエストリーの櫻田です。

眠っている「価値のタネ」を顧客の支持する価値(=顧客価値)として育てるには、
他のものと組み合わせることが大事という話です。
組み合わせることは編集力、翻訳力といってもいいかもしれません。
ブランディンではこの力を活用することがすごく大事です。
生まれたふるさとのことを書くのは意外と難しいのですが、
今回は僕が生まれたところのことを書こうと思います。
地名は中巨摩郡櫛形町、甲府から国道52号線を下り、30分ほど言ったところです。
地名の由来になった横に平べったい櫛のような山が右手に見えてきます。
山に刻まれた尾根が櫛の歯に見えなくもないのです。

櫛型山の標高は2,052m、結構高い山なんです。
僕も何度か登りましたが、頂上近くには東洋一といわれるあやめの群生地があります
(最近ではシカの食害で減少しているとか)。
あやめ以外にも高山植物が豊かで、頂上のお花畑はなかなかの見ごたえですよ。
そんなところが生まれ故郷なのですが、
2003年に4町2村の合併で「南アルプス市」が誕生しました。
この名称は公募で決まったようですが、
決まるまでの経緯や名称に対するいろいろな評価があり、難産での船出でした。
町村合併は時代の流れですから仕方がありませんが、
僕も正直言ってこの名称には最初は抵抗がありましたね。
アルプスと言う単語からはスイスのハイジを思い浮かび、
山深いところのような感じを抱かれると思ったのです。
南アルプス市に決まった経緯はよく知りませんが、いまではこの名前はすっかり定着しました。
驚いたのはいまでは、略して「南ア市」や「南プス」というのだそうです。
南アフリカか南フランスのようなイメージですよね(笑)。
しかし、「南」を入れたことは結果的には正解だと思います。
山梨、その中でもとくに勝沼といえば葡萄やワインを思い出す人が多いと思います。
実は南アルプス市は果樹の町として知られています。
実家でも僕が中学生頃までは桃やスモモを栽培していました。
春になるとピンクの桃の木の向こうに富士山が見える様子は他にない美しさだと思います。
僕の友人にもいますが、いまが最盛期のサクランボを栽培する農家も多いのです。
行政の推進もあり、「フルーツ王国・南アルプス市」というキャッチフレーズも定着しつつあります。
果物を考えて市の名前を決めたわけではないと思いますが、
果物のイメージは「中巨摩郡」と「南アルプス市」のどちらに似合うかといえばやはり後者です。
もちろん、名称変更がすべてよかったわけではなく、失われたものも少なくありません。
古い地名は消えてなくなり、それを惜しむ声もあります。
しかし、「ないもの探し」よりも「あるもの探し」、いまある条件を活かして、
足りない条件を生み出していくのがブランディングです。
その方法論が編集力、翻訳力だと思うのです。
南アルプス市→http://www.city.minami-alps.yamanashi.jp
2013年06月14日(金)更新
「岡目八目」の立場で「背中を押す」役割
「小さくても光り輝くブランド」をプロデュースしているクエストリーの櫻田です。

ちょっとわかりにくいタイトルですが、
これは僕らがブランディングプロジェクトで大事にしていることの話です。
現在もミッション、経営革新、デザイン、店舗移転など、
内容はさまざまですがいくつものブランディングプロジェクトに取り組んでいます。
僕らはブランディングの専門家ですので、
自分たちで関わったものも含めてたくさんのブランディング事例を知っています。
「こうしたらうまく行く」「こういうやり方もある」
と言ったやり方やノウハウを伝えることもできます。
しかし、僕らがブランディングプロジェクトで大事にしていることは、
「自ら考え、計画を立て、チェックして、動き出すこと」。
ですから質問はしますが、まずは相手の話をよく聞くことからプロジェクとは始まります。
話を聞くと大まかな方向が見えてきますが、それは伝えません。
それは僕らの仮説であって正しいかどうかはわからないからです。
会社の課題を一番よく知っているのは僕らではなく相手です。
相手が気付いたことが正しいと思っています。
よく知りもせず、最大公約数的な解決策を投げかけるとどうなるか?
誤解をおそれずに言いますと、相手は考えるのを止めてしまいます。
当然、動き出しはしません。答えを僕らに求めるプロジェクトになってしまいます。
プロジェクトで「おおっ」と思うのは、お取引先からたくさんの課題が出され、
その中で肝になる課題に自ら気が付く瞬間です。
こうなるとプロジェクトとは本格的に動き出します。
課題が見えるとそれを解決するためのアイデアもできる限り、相手に出してもらいます。
そのときに先ほどの事例が役に立ちます。
「こんなやり方もあります」「この方法で取り組んでいるところがあります」と言った感じですね。
プロジェクトにおける僕らの役割は二つだと思っています。
ひとつは「岡目八目」ということ。
碁を打つ本人たちには、見えないことも周りから見ると八目先まで見えることがあります。
これは大事な課題ではないなあと言うこともわかります。

もうひとつは、背中を押す役割。
僕らが引っ張るのではなく、背中を押して組織が自走できるようになることがすごく大事。
ブランコもそうですよね、後ろから押されると勢いがついてこぐことができます。
実際に自ら動き出した組織は強いですよ。
目の前の課題を、主体的に自信を持って解決していけるのですから。
これまでも動き出した組織のすごさを数々見てきました。
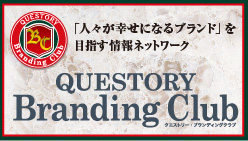

ちょっとわかりにくいタイトルですが、
これは僕らがブランディングプロジェクトで大事にしていることの話です。
現在もミッション、経営革新、デザイン、店舗移転など、
内容はさまざまですがいくつものブランディングプロジェクトに取り組んでいます。
僕らはブランディングの専門家ですので、
自分たちで関わったものも含めてたくさんのブランディング事例を知っています。
「こうしたらうまく行く」「こういうやり方もある」
と言ったやり方やノウハウを伝えることもできます。
しかし、僕らがブランディングプロジェクトで大事にしていることは、
「自ら考え、計画を立て、チェックして、動き出すこと」。
ですから質問はしますが、まずは相手の話をよく聞くことからプロジェクとは始まります。
話を聞くと大まかな方向が見えてきますが、それは伝えません。
それは僕らの仮説であって正しいかどうかはわからないからです。
会社の課題を一番よく知っているのは僕らではなく相手です。
相手が気付いたことが正しいと思っています。
よく知りもせず、最大公約数的な解決策を投げかけるとどうなるか?
誤解をおそれずに言いますと、相手は考えるのを止めてしまいます。
当然、動き出しはしません。答えを僕らに求めるプロジェクトになってしまいます。
プロジェクトで「おおっ」と思うのは、お取引先からたくさんの課題が出され、
その中で肝になる課題に自ら気が付く瞬間です。
こうなるとプロジェクトとは本格的に動き出します。
課題が見えるとそれを解決するためのアイデアもできる限り、相手に出してもらいます。
そのときに先ほどの事例が役に立ちます。
「こんなやり方もあります」「この方法で取り組んでいるところがあります」と言った感じですね。
プロジェクトにおける僕らの役割は二つだと思っています。
ひとつは「岡目八目」ということ。
碁を打つ本人たちには、見えないことも周りから見ると八目先まで見えることがあります。
これは大事な課題ではないなあと言うこともわかります。

もうひとつは、背中を押す役割。
僕らが引っ張るのではなく、背中を押して組織が自走できるようになることがすごく大事。
ブランコもそうですよね、後ろから押されると勢いがついてこぐことができます。
実際に自ら動き出した組織は強いですよ。
目の前の課題を、主体的に自信を持って解決していけるのですから。
これまでも動き出した組織のすごさを数々見てきました。
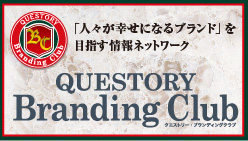
2013年06月13日(木)更新
商品調達力の格差の本質
「小さくても光り輝くブランド」をプロデュースしているクエストリーの櫻田です。

僕らの会社は小売店のブランディングの仕事が多いのですが、
最近強く感じるのは小売店の商品の調達力に格差が広がっていること。
これは小売店だけではなく、飲食店でも同じだと思います。
背景にはもちろん資本力の差もありますが、
もっと大事なことは店側の商品に向かい合う姿勢です。
店側とお客様側のギャップに気付いていないお店が多いのです。
その一例ですが、小売店の多くは大きな錯覚に陥っています。
買い物は地元でするはず、店舗に足を運ぶはず、人間関係があれば買ってくれるはず、
ライバルは同業者のはず・・・これらはもはや錯覚にすぎません。
小売店の本来の役割は、幅広い仕入れネットワークを構築し、
消費者の購買代行者として、幅広い選択肢の中から適切な商品を揃えることです。
このプロとしての姿勢の強さの優劣が、商品調達力の格差の本質だと思います。
目指すべき顧客も定まらず、要望や期待を知ろうともせず、
問屋さんやメーカーさんの勧めるものだけを仕入れているとどうなるか?
商品調達力の低い問屋さんやメーカーさんと馴れ合いでつき合っていたらどうなるのか?

商売の大事な肝である商品を選ぶ力を他人に依存してうまく行くはずがありません。
当然のことですが「選ぶ力」は次第に落ちていきます。
これはボディブローのようなもの。戦う力はどんどん失われていくのです。
そして当然のことですが、
選ぶ力が落ちれば、「選ばれる力」も比例して落ちていきます。

僕らの会社は小売店のブランディングの仕事が多いのですが、
最近強く感じるのは小売店の商品の調達力に格差が広がっていること。
これは小売店だけではなく、飲食店でも同じだと思います。
背景にはもちろん資本力の差もありますが、
もっと大事なことは店側の商品に向かい合う姿勢です。
店側とお客様側のギャップに気付いていないお店が多いのです。
その一例ですが、小売店の多くは大きな錯覚に陥っています。
買い物は地元でするはず、店舗に足を運ぶはず、人間関係があれば買ってくれるはず、
ライバルは同業者のはず・・・これらはもはや錯覚にすぎません。
小売店の本来の役割は、幅広い仕入れネットワークを構築し、
消費者の購買代行者として、幅広い選択肢の中から適切な商品を揃えることです。
このプロとしての姿勢の強さの優劣が、商品調達力の格差の本質だと思います。
目指すべき顧客も定まらず、要望や期待を知ろうともせず、
問屋さんやメーカーさんの勧めるものだけを仕入れているとどうなるか?
商品調達力の低い問屋さんやメーカーさんと馴れ合いでつき合っていたらどうなるのか?

商売の大事な肝である商品を選ぶ力を他人に依存してうまく行くはずがありません。
当然のことですが「選ぶ力」は次第に落ちていきます。
これはボディブローのようなもの。戦う力はどんどん失われていくのです。
そして当然のことですが、
選ぶ力が落ちれば、「選ばれる力」も比例して落ちていきます。
2013年06月12日(水)更新
せっかく入った店を利用することなく出てしまった理由
「小さくても光り輝くブランド」をプロデュースしているクエストリーの櫻田です。
お店で待たされるのはよくあることです。
自分ではわりかし辛抱強いほうだと思うし、
期待が高い時には待たされても「仕方がないなあ」と思います。
しかし、店の接客に怒りを覚えて、
せっかく入った店を利用することなく出たことがあります。
一度は6年ほど前のこと。店は会社の近くに出来たフレンチレストラン。
結構、お客様が入っていてインターネットでもおいしいという評判。
スケルトンのウィンドウ越しに見ると雰囲気もなかなかよさそうな店でした。
オープンして1ヶ月ほどたって、結構いいお値段だったけどランチを食べよう
ということで会社のメンバーといっしょに出かけました。
店の前に行って外からも見ると案の上、満席状態です。
ランチなのでしばらく待てば空くかなと思い店内に入ったときのことです。
ウェイターが手のひらをこちらに向け、
言葉をかけることなくストップといわんばかりに中に入るのを止める仕草。

確かに仕草にていねい(気取っていると言った方がいいかもしれません)ですが、
手のひらで入るのを止める傲慢とも思える態度にモノも言わずに店を出ました。
だからということではないのですが、このお店は数年で店じまいしました。
もう一度は自宅の最寄り駅の中によくあるパン屋さん。
この店には飲み物をオーダーすれば購入したパンを食べることができるコーナー奥にありました。
店内に入ったのは土曜日の朝でしたが、スタッフは40代の女性のみ。
さほど込んではいないのですが、パンの販売と飲み物の対応でスタッフはあわただしい動きです。
パンをトレイに載せて、レジで紅茶をオーダーしようとすると、
こちらがいるのに気が付いているはずなのに、
声をかけることもなくぷいっと奥のコーナーに行ってしまいました。
その冷たいと思える無関心な態度に思わずパンを元に戻して(かなり乱暴にね)
その店を後にしたのは言うまでもありません。
その後二度とこの店は利用していないなあ。
どちらの店にも欠落しているのは、「笑顔」と「ひと声」です。
この二つさえあれば、いやどちらか一つでもあれば、
僕は店を出ることはありませんでした。
本当に残念だと思うなあ。
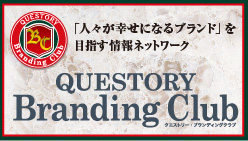
お店で待たされるのはよくあることです。
自分ではわりかし辛抱強いほうだと思うし、
期待が高い時には待たされても「仕方がないなあ」と思います。
しかし、店の接客に怒りを覚えて、
せっかく入った店を利用することなく出たことがあります。
一度は6年ほど前のこと。店は会社の近くに出来たフレンチレストラン。
結構、お客様が入っていてインターネットでもおいしいという評判。
スケルトンのウィンドウ越しに見ると雰囲気もなかなかよさそうな店でした。
オープンして1ヶ月ほどたって、結構いいお値段だったけどランチを食べよう
ということで会社のメンバーといっしょに出かけました。
店の前に行って外からも見ると案の上、満席状態です。
ランチなのでしばらく待てば空くかなと思い店内に入ったときのことです。
ウェイターが手のひらをこちらに向け、
言葉をかけることなくストップといわんばかりに中に入るのを止める仕草。

確かに仕草にていねい(気取っていると言った方がいいかもしれません)ですが、
手のひらで入るのを止める傲慢とも思える態度にモノも言わずに店を出ました。
だからということではないのですが、このお店は数年で店じまいしました。
もう一度は自宅の最寄り駅の中によくあるパン屋さん。
この店には飲み物をオーダーすれば購入したパンを食べることができるコーナー奥にありました。
店内に入ったのは土曜日の朝でしたが、スタッフは40代の女性のみ。
さほど込んではいないのですが、パンの販売と飲み物の対応でスタッフはあわただしい動きです。
パンをトレイに載せて、レジで紅茶をオーダーしようとすると、
こちらがいるのに気が付いているはずなのに、
声をかけることもなくぷいっと奥のコーナーに行ってしまいました。
その冷たいと思える無関心な態度に思わずパンを元に戻して(かなり乱暴にね)
その店を後にしたのは言うまでもありません。
その後二度とこの店は利用していないなあ。
どちらの店にも欠落しているのは、「笑顔」と「ひと声」です。
この二つさえあれば、いやどちらか一つでもあれば、
僕は店を出ることはありませんでした。
本当に残念だと思うなあ。
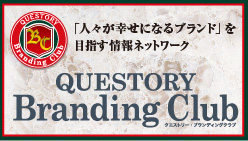
2013年06月05日(水)更新
「中巨摩郡」と「南アルプス市」のイメージの違い
「小さくても光り輝くブランド」をプロデュースしているクエストリーの櫻田です。

眠っている「価値のタネ」を顧客の支持する価値(=顧客価値)として育てるには、
他のものと組み合わせることが大事という話です。
組み合わせることは編集力、翻訳力といってもいいかもしれません。
ブランディンではこの力を活用することがすごく大事です。
生まれたふるさとのことを書くのは意外と難しいのですが、
今回は僕が生まれたところのことを書こうと思います。
地名は中巨摩郡櫛形町、甲府から国道52号線を下り、30分ほど言ったところです。
地名の由来になった横に平べったい櫛のような山が右手に見えてきます。
山に刻まれた尾根が櫛の歯に見えなくもないのです。

櫛型山の標高は2,052m、結構高い山なんです。
僕も何度か登りましたが、頂上近くには東洋一といわれるあやめの群生地があります
(最近ではシカの食害で減少しているとか)。
あやめ以外にも高山植物が豊かで、頂上のお花畑はなかなかの見ごたえですよ。
そんなところが生まれ故郷なのですが、
2003年に4町2村の合併で「南アルプス市」が誕生しました。
この名称は公募で決まったようですが、
決まるまでの経緯や名称に対するいろいろな評価があり、難産での船出でした。
町村合併は時代の流れですから仕方がありませんが、
僕も正直言ってこの名称には最初は抵抗がありましたね。
アルプスと言う単語からはスイスのハイジを思い浮かび、
山深いところのような感じを抱かれると思ったのです。
南アルプス市に決まった経緯はよく知りませんが、いまではこの名前はすっかり定着しました。
驚いたのはいまでは、略して「南ア市」や「南プス」というのだそうです。
南アフリカか南フランスのようなイメージですよね(笑)。
しかし、「南」を入れたことは結果的には正解だと思います。
山梨、その中でもとくに勝沼といえば葡萄やワインを思い出す人が多いと思います。
実は南アルプス市は果樹の町として知られています。
実家でも僕が中学生頃までは桃やスモモを栽培していました。
春になるとピンクの桃の木の向こうに富士山が見える様子は他にない美しさだと思います。
僕の友人にもいますが、いまが最盛期のサクランボを栽培する農家も多いのです。
行政の推進もあり、「フルーツ王国・南アルプス市」というキャッチフレーズも定着しつつあります。
果物を考えて市の名前を決めたわけではないと思いますが、
果物のイメージは「中巨摩郡」と「南アルプス市」のどちらに似合うかといえばやはり後者です。
もちろん、名称変更がすべてよかったわけではなく、失われたものも少なくありません。
古い地名は消えてなくなり、それを惜しむ声もあります。
しかし、「ないもの探し」よりも「あるもの探し」、いまある条件を活かして、
足りない条件を生み出していくのがブランディングです。
その方法論が編集力、翻訳力だと思うのです。
南アルプス市→http://www.city.minami-alps.yamanashi.jp
2013年06月04日(火)更新
「ロゴマーク」は幸せの記憶のスタンプ
「小さくても光り輝くブランド」をプロデュースしているクエストリーの櫻田です。
下のロゴマークを見て心が踊る男子(最近では女子もね)は相当いると思います。
そうです、そうです、プラモデルの田宮模型のロゴマークです。

僕も小学校の高学年の時にプラモデルにはまりました。
そのパッケージに書かれていたのがこのロゴでした。
田宮模型の現在の社名は株式会社タミヤ。
1946年に田宮義雄氏が創業した「田宮商事」を前身とする世界でも有数の総合模型メーカーです。
田宮模型のプラモデルへのこだわりはいくつもの伝説を生み出しています。
例えば、戦車のプラモデルのために世界の博物館をめぐり写真を撮りまくった話、
ポルシェのプラモデルのために実車を購入してバラバラに分解した話、
模型メーカーで唯一F1マシンの設計図面を見せてもらえたと言う話
(いまでは難しくなったようですが)・・・。
と言っても、一部のマニアを満足させるプラモデルではなく、
同社の製品開発のコンセプトは「初心者にも分かりやすく作りやすいプラモデル」。
顧客の立場を大事にし、企画から金型製作、ボックスアートまで
自社で一貫して作る体制を取っているそうです。
赤と青の地色に白抜きのシンプルな「ツインスター」の
ロゴマークが使われるようになったのは1966年からのこと、
50年近く経ったいまでも古さを感じませんね。
ちなみに赤は「情熱」を、青は「精密」を意味し、
それを欧文の「TAMIYA」が支えているデザインです。
これをデザインしたのは創業者の田宮義男氏の次男の田宮督夫氏
(2代目社長で現会長の田宮俊作氏の弟)です。
当時は東京芸術大学のデザイン科の学生だったそうです。
このロゴマークは日本のみならず世界の模型ショップの店頭を飾っているとか。
言うなれば、田宮模型のロゴマークが業種を表すアイコンになっているのですね。
ブランドとは「幸せの記憶のスタンプ」と言うのが弊社の基本的な考えですが、
ロゴマークはその象徴なのかもしれません。
それを田宮模型のロゴマークが教えてくれます。
下のロゴマークを見て心が踊る男子(最近では女子もね)は相当いると思います。
そうです、そうです、プラモデルの田宮模型のロゴマークです。

僕も小学校の高学年の時にプラモデルにはまりました。
そのパッケージに書かれていたのがこのロゴでした。
田宮模型の現在の社名は株式会社タミヤ。
1946年に田宮義雄氏が創業した「田宮商事」を前身とする世界でも有数の総合模型メーカーです。
田宮模型のプラモデルへのこだわりはいくつもの伝説を生み出しています。
例えば、戦車のプラモデルのために世界の博物館をめぐり写真を撮りまくった話、
ポルシェのプラモデルのために実車を購入してバラバラに分解した話、
模型メーカーで唯一F1マシンの設計図面を見せてもらえたと言う話
(いまでは難しくなったようですが)・・・。
と言っても、一部のマニアを満足させるプラモデルではなく、
同社の製品開発のコンセプトは「初心者にも分かりやすく作りやすいプラモデル」。
顧客の立場を大事にし、企画から金型製作、ボックスアートまで
自社で一貫して作る体制を取っているそうです。
赤と青の地色に白抜きのシンプルな「ツインスター」の
ロゴマークが使われるようになったのは1966年からのこと、
50年近く経ったいまでも古さを感じませんね。
ちなみに赤は「情熱」を、青は「精密」を意味し、
それを欧文の「TAMIYA」が支えているデザインです。
これをデザインしたのは創業者の田宮義男氏の次男の田宮督夫氏
(2代目社長で現会長の田宮俊作氏の弟)です。
当時は東京芸術大学のデザイン科の学生だったそうです。
このロゴマークは日本のみならず世界の模型ショップの店頭を飾っているとか。
言うなれば、田宮模型のロゴマークが業種を表すアイコンになっているのですね。
ブランドとは「幸せの記憶のスタンプ」と言うのが弊社の基本的な考えですが、
ロゴマークはその象徴なのかもしれません。
それを田宮模型のロゴマークが教えてくれます。
| «前へ | 次へ» |
 ログイン
ログイン